IoT
RFIDとは? 仕組みやメリット・デメリットを解説
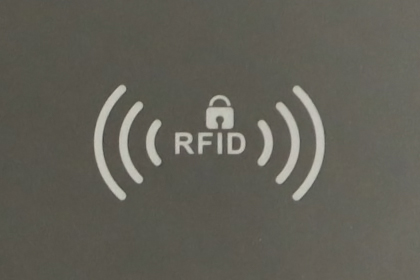
電波を使った通信によってタグに格納されたID情報を非接触で読み取る「RFID」。今、その用途が広がりを見せ、業務効率化の推進や新サービスの創出などに活用されつつあります。RFIDとはどのような技術なのか、その仕組みやメリット・デメリットについて解説します。
RFIDとは
RFID(Radio Frequency Identification)とは、近距離の無線通信を用いて、ID情報などのデータを記録した専用タグと非接触による情報のやりとりをする技術の総称です。人を介さずに専用タグからデータを読み込んで内容を認識する自動認識技術のひとつとして知られています。
専用タグはRFタグ、もしくはRFIDタグ、ICタグなどと呼ばれます。このタグはデータを書き込めるICチップ、アンテナ、コンデンサなどで構成されています。専用の読み込み装置であるリーダライタを使えば、タグとの間で近距離無線通信が行われて情報がやりとりできるという仕組みです。
身近なRFIDの活用例としては交通系ICカードや高速道路のETCカード、社員証などの非接触ICカード、車のスマートキーなどが挙げられます。また、詳しくは後述しますが、在庫管理や棚卸しにもRFIDは利用されています。
バーコードとは何が違う? RFIDの仕組みと特徴
RFIDは以前から使われているバーコードとよく比較されます。その違いはどこにあるのでしょうか。
バーコードは数字やアルファベット文字などの情報をバーとスペースの組み合わせで表し、それをバーコードスキャナーの光センサーで読み取ります。バーコードが持てる情報はごく小量で、スキャナーが発する光を遮ると読み取りができなくなり、さらに一度対象物に印刷するとその情報は変更できません。
それに対して、RFIDはRFタグとリーダライタ間で通信を行います。RFタグの記憶容量は数数10バイト〜数キロバイトと大容量で、通信なので多少の障害物があっても読み取れますし、データを書き換えられるタイプもあります。
RFIDのRFタグには、電池を持たないパッシブタグ、電池が内蔵されているアクティブタグ、両者の特徴を併せ持つセミアクティブタグの3種類があります。電池のないパッシブタグでもリーダライタを近づけると電磁誘導で起動し、通信が始まります。
RFIDの種類
RFIDには上述したRFタグの種類のほかにも、通信方式、アクセス方式、周波数帯などによってさまざまな種類があります。
通信方式は、電磁結合方式(相互誘導方式)、電磁誘導方式(誘導電磁界方式)、電波方式(放射電磁界方式)の3種類があります。電磁結合方式はタグとリーダライタそれぞれのコイル間に生じた相互誘導を利用する通信方式、電磁誘導方式は誘導磁束を利用する通信方式、電波方式は電波を利用する通信方式です。
アクセス方式は、読み取り専用のリードオンリー型、一度だけデータの書き込みが可能なライトワンス型、何回でもデータの書き換えができるリードライト型があります。
周波数帯は、LF帯(135KHz以下の長波帯)、HF帯(13.56MHzの短波帯)、UHF帯、マイクロ波帯の4種類があります。
RFIDのメリット
RFIDのメリットとして挙げられるのは、主に以下の4点です。
離れた場所からでも読み取れる
RFIDは数メートルから数十メートル距離が離れていてもデータの読み取りが可能です。そのため、例えば倉庫内の高い棚の上などに置かれた商品のRFタグとも通信が可能です。
箱の外からでも読み取れる
RFIDは通信が届く範囲であれば、障害物があってもデータを読み取れます。商品がダンボール箱に入っている場合でも、箱から取り出すことなく読み取り作業を行えます。
汚れに強い
タグ表面の表示を読み取るわけではないので、RFタグが汚れていたとしてもほとんど問題なくデータを取得できます。汚れが付きやすい現場で使えるのもRFIDの強みです。
複数のタグを一括読み込みできる
RFIDは複数のRFタグを一度にスキャニングできます。一つ一つの商品にリーダライタをかざしていくといった手間はかかりません。
RFIDのデメリット
一方、デメリットには以下のようなことがあります。
コストが高くなる
RFIDの導入にはデータ管理用のPC、リーダライタ、RFタグの購入コストがかかります。とくに大量の商品のすべてに、バーコードよりも単価の高いRFタグを付けるとなるとかなりのコストを要することになります。
読み取り精度が問題になることも
RFIDは金属の近くに置くと通信が干渉を受けたり、水分を多く含むものに貼付すると精度が落ちたりするなど、環境によっては正しく通信が行われないことがあります。棚卸しや検品にRFIDを活用する場合、仮に読み込みに失敗したRFタグがあると、在庫数が合わなくなってしまうという問題が生じます。
業務効率化に貢献! RFIDの導入事例
RFIDにはデメリットもあるものの、そのことを理解した上で上手く活用すれば、業務効率化などに役立てられます。
製造業や運輸業、小売業などでは、在庫管理、物品管理、所在管理、物流管理などにRFIDを導入するケースが増えています。
倉庫で保管している製品にRFタグをつけて管理すれば、いつでも正確な在庫数が確認でき、棚卸も簡便化できるでしょう。商品にRFタグを貼り付けて、出入り口にリーダー装置を設置しておけば、商品の持ち出し防止策としても活用できます。また、アパレル店などでは、RFIDを用いて複数の商品情報を一度に読み取って精算ができる無人レジ(バーコードを読み取るセルフレジとは別物)を実現している事例があります。
今後、コンビニなどでもRFIDの利用が増えると、無人レジだけではなく、さまざまな新しいサービスが可能になると予測されています。例えば商品棚に設置されたリーダーがRFタグの情報を自動的に読み取り、消費・賞味期限が迫っている商品を特定してユーザーに通知、その商品を購入したユーザーは値引きやポイント還元サービスを受けられるようにすると、食品ロスの削減につなげられる可能性があります。
将来は、今よりもさらに多くの商品にRFタグが搭載され、IoT技術との組み合わせでモノと人がネットワークでつながるようになるでしょう。その過程でさらに多くのビジネスアイデアも生まれると考えられます。
かつては、商品の値段を一つひとつレジで手打ちしていましたが、今やほとんどすべての商品にバーコードがつけられ、会計のスピードや正確性が大きく改善されました。それと同様に、新しい技術であるRFIDは大きな可能性を秘めているといえます。今後、普及が進むにつれ、低コスト化されることも期待できます。RFIDのメリット・デメリットを理解し、業務やサービスに役立てる方法を考えてみてはいかがでしょうか。