IoT
スマートファクトリーとは? メリット・デメリットや今後の展望など
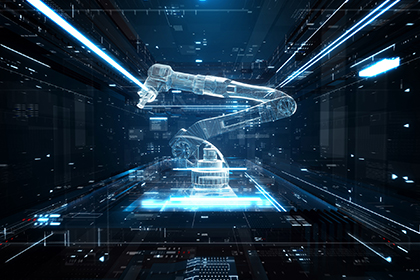
グローバル競争にさらされる製造業にとって、スマートファクトリーの導入は必須であり急務の課題ともいわれています。スマートファクトリーという用語の概要、メリットとデメリット、今後の展望などについて解説します。
スマートファクトリーとは
スマートファクトリーとは、IoT、ビッグデータ、AI、ロボットなどの活用によって、製造プロセスの自動化(無人化)、生産性や品質の向上などを実現する先進的な工場のことです。
スマートファクトリーはまた、ドイツ政府が提唱する国家プロジェクト「インダストリー4.0(第四次産業革命の意)」の中心的なコンセプトでもあります。インダストリー4.0におけるスマートファクトリーは「考える工場」ともいわれ、IoTによってデータを収集・蓄積し、AIなどが分析した結果を製造現場にフィールドバックして活用する「サイバーフィジカルシステム」を導入したものとされています。
スマートファクトリーやインダストリー4.0の考え方は世界各国に影響を与えており、日本でも経済産業省などが中心になって「コネクテッド・インダストリーズ」を提唱、また「スマートファクトリーロードマップ」を策定するなどの取り組みを行っています。
スマートファクトリー化で得られるメリット
スマートファクトリーは製造の現場をどのように変化させるのでしょうか。まず、工場がスマートファクトリー化することで得られる主なメリットを挙げてみます。
製造プロセスの見える化
各種センサーを備えたIoT端末などによる常時観測・監視を実施することで、工場における製造プロセスの見える化が実現できます。生産ラインの稼働効率や人による作業の進捗状況の把握のほか、機械や設備の特定部品の状況をカメラやセンサーで観測・監視してAI分析することで、機器が劣化する予兆を見つける予知保全も可能になります。
生産性向上
見える化とも連動しますが、設備や人の稼働率を最適化させ、無駄な作業の削減や負担を軽減し、故障・トラブルによる稼働停止を削減することで、工場としての生産性を上げることができます。また、設備と人の非稼働時間が発生する要因を突き止めるなどすれば、設備の稼働計画や人の作業計画を改善して生産性向上に役立てられます。さらに、生産計画と生産実績のギャップを精査することにより、多品種少量化時代にマッチした最適投入計画の立案も容易になります。
自動化による省人化
検品、故障検知、製造作業、計画立案などさまざまな自動化領域が拡大することによって省人化を推進できます。全てではありませんが、これまで人の勘や経験に頼っていたことも機械やシステムに任せられるようになり、余剰となった人員は人の判断や特殊な技能が必要な付加価値の高い業務に振り分けられます。
人材育成
スマートファクトリー化はものづくりの技能継承などの人材育成にも役立ちます。ベテランの技能をAIに学習させて若手技能者の作業品質の判定や分析、また従業員ごとの知識や熟練度の情報を蓄積し、データベース化して活用することが可能です。
スマートファクトリー化のデメリット・注意点
一方、スマートファクトリー化のデメリットや注意点も知っておきましょう。
まず挙げられるのは、抜本的な大改革を行うような形でスマートファクトリー化を一気に推し進めようとすると、非常に高度なグラウンドデザインが必要になるということです。すでに製造実行システム(MES。生産資源の配分や監視、工程管理、データ収集などを行って製造現場を支援するシステム)やファクトリーオートメーション(FA。工場の生産工程を自動化するシステム)などを積極的に導入している大企業などであれば、スマートファクトリー化への道筋も見つけやすいのですが、対応が遅れている中小企業にはこの方法はハードルが高いはずです。
そもそも、それぞれの製造現場に最適なデータの収集、分析、活用の方法を決めるのも容易なことではありません。当初はある程度の試行錯誤を強いられるでしょう。その点も含めて、設備投資やシステムを扱える人材の確保・育成のコストは多大なものになります。生産性向上などにはIoTやAI技術の活用がカギとなるのは確かですが、その機能を的確に活かすことができなければ導入が逆の結果を招かないとも限りません。
こうした問題を回避するために有効なのは、信頼できるシステム開発会社、実績のあるIoTプラットフォームなどの活用、そして最初は目的を最小限に絞ってスモールスタートによる導入を実施することでしょう。
日本国内におけるスマートファクトリーの現状と展望
経済産業省の「スマートファクトリーロードマップ」は、IoTなどを活用したものづくりのスマート化の方向性、スマートファクトリー化を進めるにあたっての成功ポイントなどを整理した資料として参考になります。
同ロードマップでは、スマートファクトリー化の目的として品質の向上、コストの削減、生産性の向上、製品化・量産化の期間短縮、人材不足・育成への対応、新たな付加価値の提供・提供価値の向上、その他(リスク管理の強化)を挙げています。また、それぞれの目的別にさらに具体的な目的を抽出し、レベル1、レベル2、レベル3とスマート化のレベル(データ活用のレベル)別のポイントを示しています。
同じく経済産業省の「製造基盤白書(ものづくり白書)」も、俯瞰的な国内の製造業の現状把握に役立ちます。Webページには実際にものづくりの現場で行われているデジタル技術の活用、良好な人材育成の推進、熟練技能の継承の取り組みに関する事例も掲載されています。
その一つとして紹介されているのが、ある地方の総合工作機械メーカーの事例です。超多品種少量生産を行う同社では、2013年から2019年にかけて順次3つの工場を立ち上げてきました。第1の工場では生産設備の自動化・無人化と稼働状況の見える化に取り組み、第2の工場ではロボットやIoTの活用、「進捗・稼働状況監視システム」を含む工場コントローラの導入などにより72時間無人稼働を実現、第3の工場ではレーザ焼入れ機能を有する超複合加工機などによって工程集約をさらに推進するなど、段階的かつ着実にスマートファクトリー化へのプロセスをたどっています。
また、一方で同社では、社内の熟練の技を磨くための取り組みや技能伝承にも積極的に取り組んでいます。デジタル化と熟練の技の融合を大目標に掲げており、こうした点もスマートファクトリー化をめざす製造業者にとって参考になるのではないでしょうか。
また、小規模な投資でのスマートファクトリー化の例として、医療施設向けのパッケージ(袋)を製造する企業の事例があります。IoTデバイスをシーリング機に取り付けて、「稼働モニタリングシステム」を構築する取り組みです。IoTデバイスは、数千円の市販マイコンボードに光センサーと無線発信機を組み合わせたという比較的簡易なものです。それでも、当システムの構築によって機械トラブルや生産状況の稼働状況をリアルタイムで確認でき、トラブル時に管理者が即時対応可能となり、機械の稼働率向上につながったといいます。
スマートファクトリーは未来の技術ではなく、今、企業が抱えている課題を解決するために取り組むべき現場改革です。製造現場のどの部分をどのようにスマート化するのか、そこから検討を始めてみてはいかがでしょうか。