IoT
無線モジュールとは? IoT機器に組み込むメリットと注意点
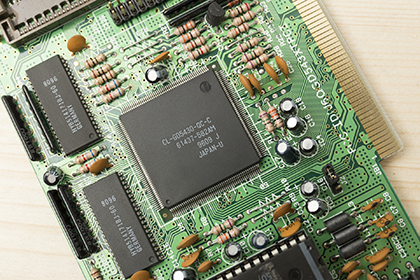
多くのIoT機器が備えている無線通信機能。しかし、IoT機器の開発とあわせて無線回路をチューニングし、無線を可能にするソフトウェアを新規設計するには専門的なノウハウと開発期間が必要になります。そこで活用したいのが、さまざまなメーカーから発売されている「無線モジュール」です。無線モジュールとはどのようなもので、IoT機器に組み込むとどんなメリットが得られるのか、解説します。
無線モジュールとは
無線モジュールとは、無線通信に使用する無線チップや周辺回路を小型の基板に搭載し、通信機能を制御するコントローラーとソフトウェアまでがセットになった電子部品です。このモジュールを部品として使用すれば、無線回路の調整やソフトウェアの新規設計を行うことなく、自社製品に無線機能を付加することができます。
通信モジュールがサポートする周波数帯域には、Wi-FiやBluetoothでよく利用されている2.4GHzと、サブギガ帯と呼ばれる920MHzがあります。2.4GHzは比較的大容量のデータを扱う場合に、920MHzは障害物が多い場所で多数かつ小容量のデータを扱う場合に適しています。またほかにも、426MHz、429MHz、315MHz、1.2GHzなどの周波数帯域に対応した通信モジュールも作られています。
さらに、ハードインターフェイス、周波数チャネル、データ変調速度、伝送距離、通信方式、通信形態、送信出力、消費電流といったスペックの違い、アンテナが外付けか内蔵か、もしくは複数のアンテナを利用できるダイバーシティタイプといった選択肢もあります。いまでは各社から多数の通信モジュールが販売されており、豊富なラインアップから適したものを選ぶことが可能です。
IoT機器に組み込まれる無線モジュール
スマートフォン、タブレットなどの情報端末、PC周辺機器などにも使用される無線モジュールですが、近年、IoT機器に組み込むという用途によって著しく需要が伸びています。IoT機器を開発する際に無線モジュールを利用すれば、開発工数と開発期間を削減しつつ無線通信機能を容易に実装できるからです。
IoT機器に組み込むことを想定して開発される無線モジュールも急増しています。たとえばIoT機器は基本的に電池駆動を前提とするため、優れた低消費電力化を実現した無線モジュールが注目されています。これはセンサーやマイコンの消費電力と比較して、無線回路の消費電力が非常に大きいことと関係があります。そのため通信頻度を制御し、必要に応じてスリープモードやシャットダウン機能を活用するなど、待機電力をできるだけ抑える工夫がなされた無線モジュールが登場しています。
IoT機器に無線モジュールを組み込むメリット
IoT機器に無線モジュールを組み込むメリットを改めて整理してみましょう。
まず挙げられるのはすでに述べてきたように、無線回路の調整やソフトウェアの設計をしなくても、無線対応のIoT機器の開発・生産が可能になる点です。とくにアナログ回路である無線回路のチューニングは、基板や周辺回路との相性などがあり、専門的な技術やノウハウが欠かせません。無線通信機器開発の経験が少ないメーカーほど、そのプロセスが省けることによる恩恵は大きいといえます。
また、無線通信機器の開発に際して取得しなければならない認定作業が不要になる点もメリットです。日本国内で電波を利用する機器を開発する際は、一般社団法人電波産業会が定める「標準規格(ARIBスタンダード)」を遵守する必要があります。また、電波法により「技術基準適合証明(技適)」の認証も取得しなくてはなりません。
国内で販売されている無線モジュールであれば、ほとんどの製品が2つの認定を受けています。そのためIoT機器メーカーは申請手続きなどに要する手間を省くことができます。
IoT機器に無線モジュールを組み込む際の注意点
IoT機器に無線モジュールを組み込む際は、IoT機器の用途に合わせて最適な周波数帯域を選ぶことが重要です。たとえば監視カメラなど映像データを送るのであれば比較的大容量のデータを送れる2.4GHzの周波数帯域が向いていると考えられます。
一方、多数のセンサからデータを収集するような場合は、障害物を迂回する回り込み特性に優れていて消費電力を低く抑えられる920MHzの周波数帯域が適しているでしょう。とくに最近、IoT機器に多く利用されるようになっているのが、920MHz帯の無線モジュールです。920MHz帯無線は、2.4GHz帯無線ほど多くの機器に使用されていないので混線などが少ないというメリットもあります。
周波数帯とあわせて、利用する通信規格も選定しなくてはなりません。2.4GHz帯無線にはWi-Fi、Bluetooth、ZigBeeなどが選択肢にあり、それぞれ消費電力や通信距離などの特性が異なります。とくにZigBeeは省電力性に優れ、多数のセンサを接続して構成するセンサネットワークに適した通信規格として知られています。920MHz帯無線には電波産業会(ARIB)により2012年2月に策定されたARIB STD-T108という規格があります。
通信距離を長くしたい場合は、マルチホップに対応した無線モジュールの採用も検討してみましょう。マルチホップは中継機を介してデータをバケツリレーのように転送していく無線方式です。
さらに、忘れてはならないのがセキュリティです。IoT機器の用途にもよりますが、データの傍受などを防ぐために、データの暗号化やネットワークに接続する際の認証機能が備わっているかどうかも製品選択の際に確認しておきましょう。
無線モジュールを利用すれば、IoT機器の開発期間の短縮が見込めます。自社製品に適した無線モジュールを選び、その性能を賢く活用してください。
※「ARIB」は、一般社団法人電波産業会の商標または登録商標です。
※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
※「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。
※「ZigBee」は、ZigBee Alliance, Inc. の商標または登録商標です 。