経営戦略
残業を減らして生産性向上! 長時間労働を改善する方法
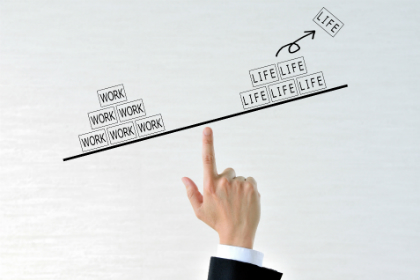
残業を減らすこと、長時間労働を改善することは日本の企業にとって今、とても重要な課題となっています。2019年4月から働き方改革関連法も施行された中で、どのようにして長時間労働を改善していくのか、その方法を探っていきます。
長時間労働の目安
結論から先に書くと、長時間労働といえる目安の一つは「月45時間以上の時間外労働」です。
時間外労働とはいわゆる残業・超過勤務のことで、より正確にいえば労働基準法などに定められた法定労働時間を超える労働を指す言葉です。
法定労働時間は、原則1日8時間、1週間40時間以内です。また使用者は労働者に毎週1回以上、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
そして本来、会社が労働者に時間外労働を命じる際は、会社と労働者側の代表者との間で「労基法36条に基づく労使協定」を締結する必要があります。この協定は労働基準法第36条が根拠になっているため、「36協定(さぶろく協定)」と呼ばれています。
この36協定における時間外労働の限度時間が、特別の事情がない限り1か月45時間(1週間15時間、1年間360時間)なのです。長時間労働の目安とされている理由がおわかりいただけましたでしょうか。
日本の労働時間に関する定め
2019年4月から労働基準法改正をはじめとする「働き方改革」が本格始動しました。その中で36協定などについても下記のような見直しがなされています。
36協定
使用者が法定労働時間を超えて残業させる場合、36協定を締結する……という基本的枠組みは変わっていません。
変わったのは、時間外労働の「罰則付き上限規制」の導入です。
改正前は、臨時的な特別の事情がある場合、特別条項を結べば時間外労働時間を増やすことができました。このとき実は、法律上、残業時間の上限はなく、月45時間、1年間360時間という基準を元にした行政指導のみにとどまっていたのです。しかし改正後は法律で上限を定めたので、これを超える残業はできなくなりました。原則1か月45時間であるとともに、特別の事情があったとしても、時間外労働が年720時間以内、時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度といった制限があります。これに違反すれば罰則が科せられます。
働き方改革関連法
ほかにも働き方改革関連法によって、次のような法改正事項が実施されています(または今後実施されます)。
- 5日間の「有給休暇取得」の義務化(2019年4月〜)
- 「勤務間インターバル制度」の導入促進(2019年4月〜)
- 「フレックスタイム制」の拡充(2019年4月〜)
- 「高度プロフェッショナル制度」の導入(2019年4月〜)
- 「産業医」の機能強化(2019年4月〜)
- 月60時間超残業に対する割増賃金率引き上げ(大企業は適用済、中小企業は2023年4月〜)
- 雇用形態にかかわらない同一労働同一賃金の原則の適用(大企業は2020年4月〜、中小企業は2021年4月〜)
長時間労働になってしまう原因
長時間労働はなぜ起きてしまうのでしょうか。原因として考えられるのは次の5つです。
1.労働人口の減少
多くの企業が人手不足に陥った結果、かつての仕事量をこなすには残業しなければ追いつかないという状況が生まれています。また必要以上に人件費を削減しようとする企業、スタートアップから間もない企業などでも人手が足りず業務過多になるケースが見られます。
2.生産性の低さ
時間内に終わるはずの作業をダラダラと続けてしまう生産性の低さも残業を生み出します。全体の業務効率が悪く、1人の作業が終わらないと、それを引き継ぐ次の担当者の作業も進められないというパターンにも陥りがちです。
3.従業員のモチベーション低下
生産性の低さは従業員の意識の低さにも起因しています。給与が安いなどの理由で、残業代を稼ぐためにわざわざ時間外に働くという人もいます。
4.長時間労働者を高く評価する職場風土
長時間労働をする従業員ほど会社に貢献している、という空気の会社もいまだに存在します。残業をする人=頑張って働く人、という認識を改めなくてはなりません。
5.残業を当然とする環境
定時になってもすぐに帰る従業員がいない会社もあります。残業が当然になっていると、サービス残業という形で時間外労働手当なしで働くケースも多く出てきます。
長時間労働を改善する方法
長時間労働を改善するには一つの方法を試すだけではなく、さまざまな角度からのアプローチが効果的です。改善のヒントになるものをご紹介します。
1.人事評価制度を見直す
人事評価制度を見直し、規定時間内での生産性の高さや成果を評価する仕組みを整備する方法です。例えば残業代はこれまでどおり支給しつつ、残業時間を減らしたり有給休暇の取得率を上げたりした従業員にはインセンティブを与えるといった制度に取り組み、成功している企業もあります。がんばっただけ給料が増える、もしくは長時間勤務時の給与水準を維持できるとなれば、業務に対する社員の意識も変えられるというわけです。
2.業務のオペレーションを見直す
業務効率が上がれば、時間外の仕事は不要になるはずです。作業の無駄を省き、アイドルタイムを減らし、限られた時間内で濃密に仕事に取り組めるようオペレーションを見直しましょう。従業員のモチベーションアップにもつながります。
3.勤務間インターバル制度の導入
終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間の休息を設定して、従業員の生活時間や睡眠時間を確保するのが勤務間インターバル制度です。働き方改革関連法では前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが、事業主の努力義務として規定されました。
4.テレワーク、朝型勤務、ノー残業デーの導入
従業員それぞれの個性に合わせて、テレワークや朝型勤務、フレックスタイム制など多様な働き方が選択できるような会社が増えています。「ノー残業デー」の導入も一般化しています。会社にも仕事中心ではなく、生活時間も含めたワークライフバランスを保つことをサポートするという意識が求められています。
長時間労働の改善に取り組むときの注意点
長時間労働の改善に取り組む際は、根本的な原因がどこにあるのかを見きわめて、その部分の改善を図ることが非常に重要です。単に毎日定時に強制的に退社させるなど、対処療法的なやり方をしても事態は改善されません。そればかりか、隠れ残業や役職者の負担増大につながる危険性が高いでしょう。
そのためにはまずは実態調査を行うことです。誰がどれくらい、どのような形で、なぜ時間外労働をしているのか、情報を集めて、実態を掴み、可視化することから始めてください。
長時間労働の改善を図るには、原因に合った対策が必要です。原因をしっかり把握した上で改善策を構築し、じっくりと腰を据えて取り組みましょう。