ワークスタイル
働き方改革の目的とは? 取り組む企業の課題と解決策
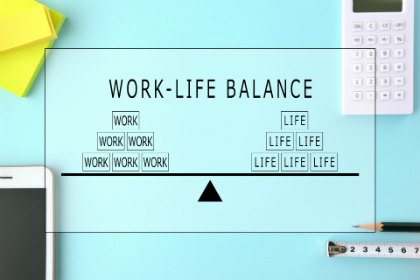
2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されています。これに伴い、企業はそれぞれの労働の現場で、具体的に「働き方改革」を推進していくこととなりました。しかし、時間外労働の短縮などに付け焼き刃的な考えで対応しようとすれば、課題と負担が増すばかりで真の改革は進みません。そこであらためて働き方改革の目的と、改革に取り組む企業の課題、解決策について考えてみます。
働き方改革とは
働き方改革とは、安倍政権が掲げる「一億総活躍社会」の実現に向けて、企業の労働環境を改善するための取り組みを指す言葉です。そのために働く人の視点に立ち、労働制度の抜本的改革、さらには企業文化や風土も含めて変えようという試みでもあります。
労働について考える上で日本が現在、直面しているのは、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「育児や介護との両立など働く人のニーズの多様化」などの状況です。これに対し、企業側も投資やイノベーションによる生産性向上を成し遂げ、同時に働き手の就業機会の拡大、意欲・能力を存分に発揮できる環境を整えることが重要な課題になっています。
厚生労働省は、働き方改革がめざすのはこれらの課題を解決するために、働く人の置かれた個々の事情に応じて多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く人、一人ひとりがより良い将来の展望をもてるようにすることとしています。
働き方改革の実現に向けて、「処遇の改善(賃金など)」、「制約の克服(時間・場所など)」、「キャリアの構築」という3つの改革のための課題を挙げて、検討テーマと現状を洗い出し対応策をまとめた2027年までのロードマップも作成されています。
そして2018年6月には働き方改革法案が成立しました。2019年4月1日から「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」が順次施行されています。
2018年6月29日に行われた会見で、安倍首相がこの法律は「長時間労働を是正していく、そして、非正規という言葉を一掃していく、子育て、あるいは介護をしながら働くことができるように、多様な働き方を可能にする法制度」と説明しました。
働き方改革の目的
働き方改革を推進する目的は、労働者にとっての「働きやすさ」を実現していくことにあります。そのためには働く人、一人ひとりの意思、能力、個々の事情に応じて、多様で柔軟な働き方を選択可能な社会を作り上げることが重要とされています。
また政府にとっては、働き方改革を進めていくことで国内の雇用促進を図り、労働者の増加によって税収を増やし、ひいては日本経済を発展させていくという大きな目的があると考えられます。
では企業にとっての目的は何かと言えば、一つは法令遵守、そして働き方改革を積極的に推進することによる労働力の確保と生産性の向上ということになるでしょう。
働きたいという意志と意欲を持つ人たちが働きやすい労働環境、社会が形成されていけば、そのことが国や企業にとっても意義のある好ましい結果をもたらす、というのが働き方改革の基本的な考え方です。
働き方改革に取り組む企業の課題
しかし、企業にとって、実際に働き方改革を導入していくことは簡単なことではありません。現時点での働き方改革関連法の3つのポイント、「時間外労働の上限規制の導入」、「年次有給休暇の確実な取得」、「正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止」を実現させようとするだけでも、次のような課題が浮かび上がってくることが考えられます。
コストアップ
仕事内容の見直し、就業規則の再整備、従業員への周知活動などが求められ、それらに費やすコストがかかります。また労働時間を抑えながら生産性を上げるためにIT設備を導入しなければならないケースも出てきます。
生産性の低下
時間外労働の上限規制に従い、単純に労働時間を短縮するだけだとこれまで通りに仕事が完遂できなくなります。生産性はむしろ低下し、競争力も落ちていくおそれがあります。これまで従業員の勤勉さや恒常的な長時間労働に頼ってきた企業ほど、その傾向は強いでしょう。
人件費の増加
生産性を確保するために従業員の増員が必要になれば、結果として人件費が膨らむことになります。人を雇わないとすれば、アウトソーシングに頼らざるを得なくなるケースも考えられます。また同一労働同一賃金の実現に伴い、非正規雇用者に対する人件費も増加します。
管理職の負担増大
従業員の長時間労働を是正するために、管理職が部下の残業時間を把握、管理しなければなりません。また、有給休暇の取得状況の把握についても同様です。
働き方改革の課題への解決策とは
上記のような課題をクリアするには、働き方改革関連法施行を受けての対処療法的な対応ではなく、働き方改革全体の趣旨を理解した上での長期的な改革計画を立てることが重要です。先を見据えて、それぞれの企業の事情を反映した上でのロードマップを作成し、戦略的に働き方改革を進めていく必要があります。
そのためには管理職、従業員へのヒアリングを行い、経営陣の方針をしっかりと定めなければなりません。コンサルティング会社など専門家の力を借りることも有効でしょう。いずれにしろ、働き方改革を人材確保や生産性向上に正しく結びつけ、企業にとって意義あるものにするには、長期的な視点に立った上での導入戦略が必須となるでしょう。
働き方改革をどのように受け入れ、咀嚼し、推し進めていくかは、これからの数年間、企業にとって大きな課題となるはずです。しっかりとした解決策を見つけていくことが求められます。